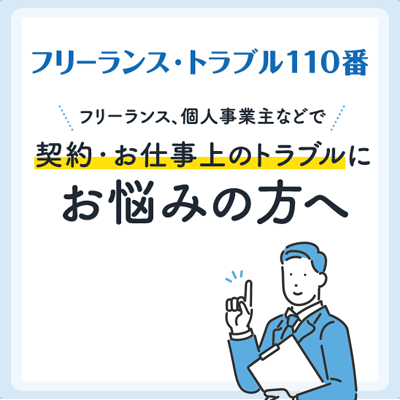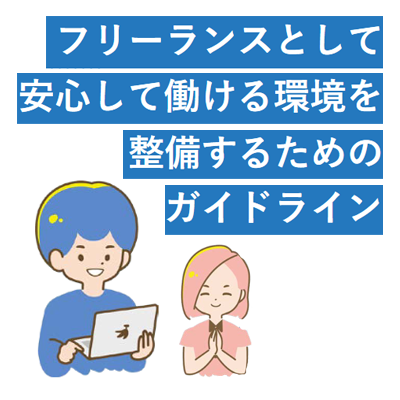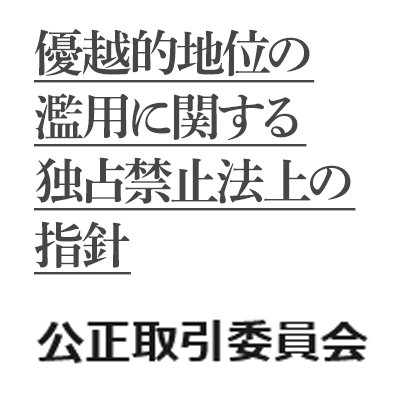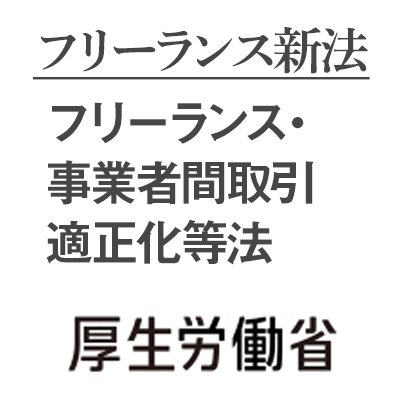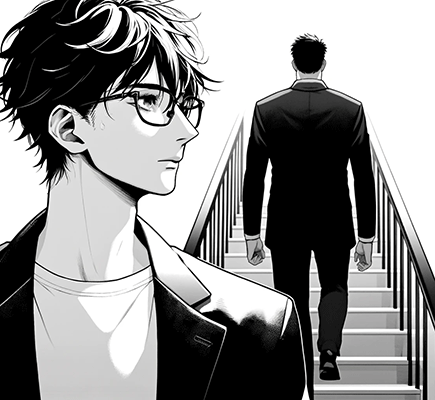
二回目の和解あっせんの話し合いは、先方企業の都合で予定より早まり、約一ヶ月後に行われました。一ヶ月後とはだいぶ間隔が空いているようにも思いますが、これでも時期を早めた結果でした。実際の裁判などになれば、次の話し合いまで数カ月先ということもあるわけです。
その間、あっせん人である弁護士とはメールで何度かやり取りがあり、初めはやや厳しい印象を受けましたが、私は真摯に応じ、必要な証拠の提出や質問に対する回答を送りました。
そして、二回目の話し合いの当日を迎えます。
一回目の和解あっせんでは、相手と直接対面することなく済みましたが、二回目の話し合いの日、弁護士会のビル内の階段で偶然、見慣れた後ろ姿を目撃します。慌てて別の方向へ避難しましたが、間違いなく相手企業の担当者の後ろ姿でした。ほぼ同時刻に同じ建物にいるため、遭遇する可能性は十分ありました。無事に避けられてホッと一息つき、少し時間を置いて控室に向かいました。
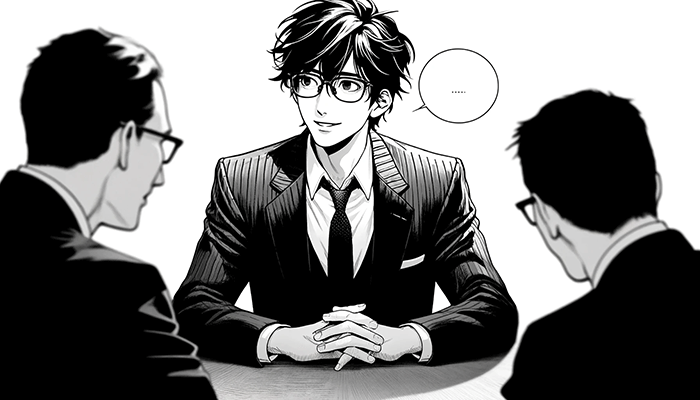
今回は前回とは異なり、迎えてくれた二人のあっせん人の弁護士の態度は穏やかでした。
彼らは既に、相手の企業の依頼の仕方や不適切な言動、案件への理解の浅さから、どちらが信頼できるかを見極めてくれたようです。
相手企業側は自らの主張が正しいと信じており、訴訟や賠償請求も辞さない姿勢だったようです。しかし、あっせん人から私の仕事の進め方には瑕疵や過失がないと判断され、さすがに折れたようで、適切な和解を勧めてくれたそうです。
この日は二人の和やかな対応に安心し、相手もこれ以上話し合いに自分たちの利益が無いとみていたようだったので、私もこの日で話し合いを終えたいと伝えました。
そこであっせん人からは、和解あっせんは「痛み分け」が前提であり、完全勝利を期待するのではなく、多少の妥協が必要です。ということを教えてもらいました。内容的にはほぼこちらの主張が理解された形にはなりましたが、和解とは「妥協と痛み分け」で五分五分の決着が基本のようなものだということでした。
納得のいかない点、納得できた点が様々ありましたが、多少の金銭的な妥協を経て、和解契約書にサインし、私の「和解あっせん」の話し合いは終了しました。