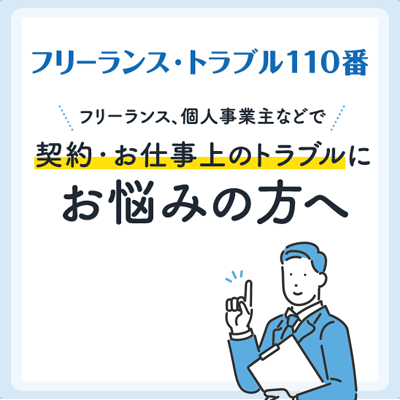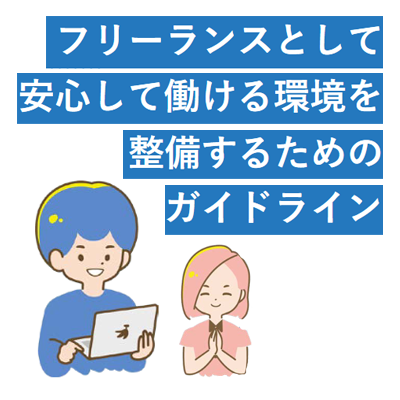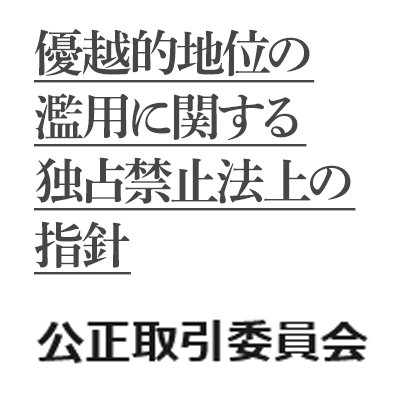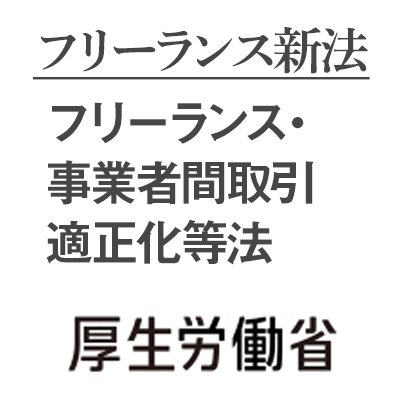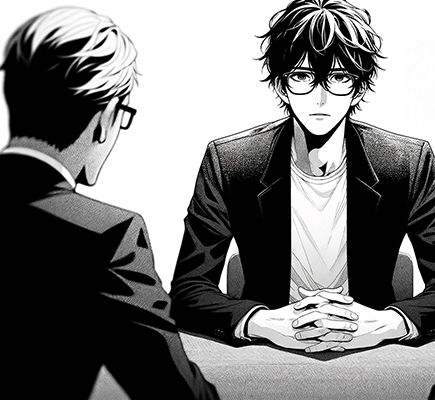
私は和解あっせんの最初の話し合いに挑みました。
先に話をしていた相手側から、私のイメージを損なうような話がされたかもしれません。想像ではなく、実際に最初の話しの場での私に対しての和解あっせん人(仲裁人弁護士)の心象は良いものではないという印象を受けました。
相手の社長が答弁書の内容に沿った話をしていたとしたら、私は徹夜で作成した反証資料に自信を持っていましたが、2人の弁護士からの最初の質問は、まったく異なったものでした。
質問は、私が今後も相手の会社と取引を続けたいか、そして、なぜ要求された作業を行わなかったのか、という点であり、いきなりこの問題の核心を捉えたものでした。それと同時に、私は用意してきていた反証資料はほとんど必要なくなったことを悟りました。
和解あっせん人である2人の弁護士へは、要件定義書にはなかった作業を相手が追加で要求してきたこと、そして、そのような不当な要求をする企業とは今後取引をする意思がないことを丁寧に説明しました。
この話し合いは、相手の会社との関係が継続する場合に話が難しくなるケースもあると聞かされました。小さなミーティングルームでの待機を数度繰り返し、最初の和解あっせんの話し合いは終了しました。
私が用意した反証のための資料は完全に無駄になり、相手のウソや虚偽の主張を暴くチャンスも失われたことが腹立たしかったです。しかし、同時に、私はただ企業側の横暴を訴えるためではなく、問題を解決するためにここに来たのだと気持ちを切り替えました。
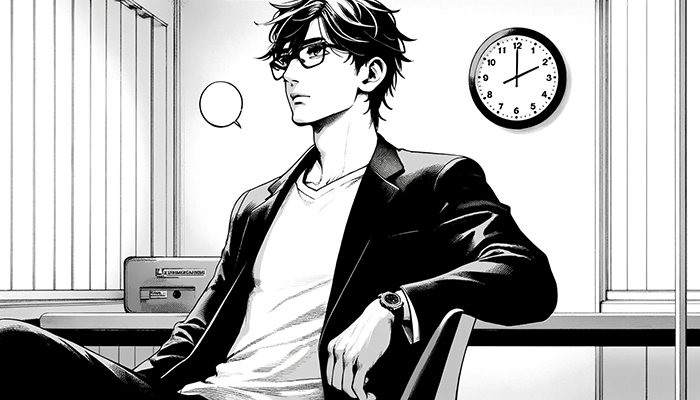
後日、和解あっせん人から質問がメールで来たので、要件定義書と見積りを同時に送っており、内容について相手企業が了承しているやり取りを送りました。
メールのやり取りの内容については企業側からも提出されていますが、事実の核心である証拠は無かったものにされていたのでしょう。和解あっせん人(仲裁人弁護士)の確認したい内容は、企業側が隠したい要件定義書と見積りの内容証拠と事実だということです。
※「要件定義書」とは、どのような内容のシステムを作るかを具体的にまとめて発注側から渡される資料です。一般的には発注書に相当するものですが、この種のシステム開発案件では発注側ではなく受注側で発注側の要望をまとめてから出され、発注元と共有されることもあります。